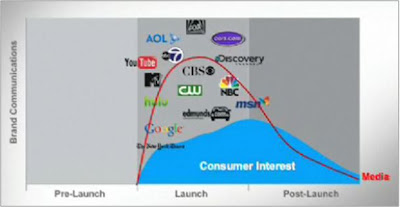昨年12月23日のMSN 産経ニュースに、「社長の座賭け、経営改革 ”脱家電”急ぐジャパネットたかた」という記事があった。
地上デジタル放送移行や家電エコポイント制度による“テレビ特需”の反動に、人気のテレビ通販会社「ジャパネットたかた」が苦しんでいる。高田明社長の独 特の語り口で、多くの消費者になじみ深い同社だが、主力の家電販売が落ち込み、売上高の低迷が続いているのだ。高田社長は平成25年12月期に最高益を達成できなければ「社長を辞める」と公言、背水の陣で新たな柱を模索しているが、答えはまだ見えていない。
国内電機メーカーや家電量販店は、テレビ特需の反動から抜け出せないでいる。パナソニック、シャープは25年3月期に合計で1兆2150億円もの最 終赤字を予想。家電量販大手もテレビ販売が7割減となるなど売り上げが低迷、最大手のヤマダ電機でさえ大幅な減収減益を余儀なくされている。
こうした状況は、売上高の8割以上を家電が占めるジャパネットたかたも変わらない。23年12月期の売上高は前年比13%減の1531億円で7期ぶりの減収。今期の売上高も前年割れとなることが確実だ。出典:MSN 産経ニュース
そして、ジャパネットたかたが2月下旬に「Webマーケティング」職を募集していた。
募集要項には、
商品の先にある豊かさや感動を全国のお客様に伝えるために、自社ショッピングサイトのSEO対策やランディングの最適化、アクセスやレスポンスの解析・検証、リスティングやアフィリエイト広告などを用いたマーケティングの立案・実施・検証を行っていただきます。とある。
ネット販売の強化を打ち出すための募集ということだろう。
そこでSimilarWebで他サイトと比較してみた。
アマゾン
楽天
ヤマダ電機
ジャパネットたかた
ついでにAlexaでも比較してみた。
アマゾン
楽天
ヤマダ電機
ジャパネットたかた
どこからどう見てもジャパネットたかたWebサイトの劣勢は否めない。
アマゾンの売上は12年で78億ドル(約7,300億円)、楽天は2,858億円(流通総額1兆3,000億円程度)。背中が見えないほど離れているこの2強を追いかけるわけだが、上のWebマーケティング職の募集要項にある内容で、良いのだろうか?
そういった募集内容をベースとしたWebマーケティングの取り組みであればアマゾンも、楽天も、ヤマダ電機もやっているはずだ。他社と同じことをやっていて、平成25年度に過去最高の経常利益136億円を越えられるのだろうか?
SEOをやったところでキーワードごとのクリック率は5%程度、他ECサイトと同じ製品・サービスを売っているとするとキーワード単価は上がらざるを得ない。LPOをやった所で高が知れている。アフィリエートをやった所で16.4%のリンク比率がアマゾンのように30%弱にまで2年間で上昇するとは思えない。バナー広告をYahoo!に出しまくればROIは超低空飛行になる。
それよりもクリックしてアクセスしてくれたユーザは、AISCEASへ移行していて検索、比較、検討という購買プロセスの一環で来ているだけだ。テレビショッピングでおまけ盛りだくさんの商品をチェックしに来たとしても、本当に欲しいものを他社ECサイトでもチェックするし、ポイントカードや他キャンペーンも考えた上で購買する。Webへ誘導したからゴールが達成されるわけではない。
そして、消費者の使用感想・評価が最終的に購買を決定する大きな影響力を及ぼしていることを理解しない限り、まだAIDMAやAISASのプロセスにいると思っている消費者の影を踏んでいるだけで、AISCEASへ移行した消費者の財布のひもを緩めることはできない。
消費者の情報発信力が飛躍的に向上し、利用者レビューが購買プロセスに大きく関り、影響している現在、SEO、LPO、アクセス解析、アフィリエート、広告といった通常のWebマーケティング、リアクティブなマーケティングをやっていても、他社が同様にやっているマーケティングをやっていても抜きんでることはできないと思うがいかがだろうか?
さて、ジャパネットたかたに関係するTwitterアカウントには、
- ジャパネットたかた媒体担当(注:2月25日にお知らせ担当へ変更)
- ジャパネットたかた採用担当
- ジャパネットたかたセール情報
- ジャパネット「WEBスタ!」スタッフ
- ジャパネット AF担当
- 高田 明
高田 明アカウントを除くと、一番フォロワー数の多い「ジャパネットたかた媒体担当」のTwitterアカウントをチェックしてみた。(注:アカウント名が2月25日にお知らせ担当へ変更されているが、画像は23日のもの)
2月23日には以下のように2,809回ツィートし、117ユーザをフォロー、3,166人からフォローされている。
ジャパネットたかた媒体担当アカウントがフォローしているのは、当然ながら、TV・ラジオ局、タレント、メーカー、スポーツ選手などがいる。一般の消費者をフォローしてはいない。
Twitterを開始したのは2011年6月。これまでの21カ月間を平均すると一日に4.6回、月に133回ツィートしている。
さて、このツィートの中身はと言うと、2,809回のツィート中の9.18%(258回)がリプライで、4.27%(120回)がリツィートだったと云うことになる。下図はそれぞれのトップ10。
リプライしたトップ10のユーザはどんなアカウントかというと、
- @honane 大阪毎日放送の未公認・非公式キャラ
- @kanakanabun 大山加奈(元バレーボール選手)
- @muneyuki_imon ラジオDJ
- @pankurojun 黒瀬純(お笑いタレント)
- japanet_1206wps
- kutv_tvkochi テレビ高知
- sanfrecce12 サンフレッチェ広島のサポートアカウント
- rnc_tvradio 西日本放送
- account_kkojima 小島慶子(タレント)
- TVTOKYO_PR テレビ東京宣伝部
- @honane 大阪毎日放送の未公認・非公式キャラ
- @A_TAKATA 高田明
- @JAPANET_media ジャパネットたかた媒体担当
- japangun
- POOOOhw
- kano9x 狩野英孝(タレント)
- STV_FF STV(札幌テレビ)広報
- ibs_radio 茨城放送
- katsuyama0611 ムーディ勝山(タレント)
- neo_sakura_eri
2,809回のうち378回を除いた2,431回(86.55%)はリプライでも、リツィートでもない自発的なツィート、「ジャパネットたかた媒体(お知らせ)担当」のアカウントなのでTV番組情報を発信していることになる。
さて、「ジャパネットたかた媒体(お知らせ)担当」はなぜ一方的な情報発信だけをするのだろうと聞けば、それは当然ながら媒体情報をお知らせする、商品情報をお知らせするアカウントだからということになる。
しかし、6つもあるアカウントすべてがなぜ消費者をフォローしていないのだろう?そして、 「商品の先にある豊かさや感動を伝える全国のお客様」がどんなことを発信しているかをモニターしていないのだろう? ジャパネットたかたが発信した情報に対してどんな感想、評価を下し、どんな発信をしているかをチェックしていないのだろう?
例えば1月29日に、416人がリツィートし、192人がお気に入りに登録したツィートがある。(数字は2月23日時点)
"ジャパネットたかたの高田社長がビデオカメラを売る際に 子どもだけじゃなくて、親の顔を撮ったほうがいい、 その子どもが大きくなったときに、自分が幼い頃なんて ぶっちゃけどうでもいいけれど、自分の誕生を両親が..." tmblr.co/ZfAAWycy7UUW
— たこじまさん (@takojima) 2013年1月29日
こういったツィートを6つあるTwitterアカウントのひとつでもRTしていれば、素晴らしいバズになったはずだ。だが、モニタリングしていないようなので、どのアカウントもRTしていない。リプライを返してはいない。本当にもったいない。このツィートはジャパネットたかたが売っている商品とは少しずれるけれど、ジャパネットたかたやその販売商品に関する消費者の評価・レビューは、一方的な広告でもなく、アフィリエートでもなく、自然発生的な消費者の声だ。この生で、未加工の声を他の消費者は信頼する。自分も納得した上でRTしたり、共有する。だからそういった声が比較・検討という購買プロセスで最も評価されるコンテンツになっている。
消費者をモニタリングし、その声を拾い、対応し、フィードバックを次の情報発信に活かすことがWebマーケティングというよりもオンラインマーケティングだと思うがいかがだろう?
また、種を蒔いて育てることも必要だ。現状を補完するためのSEO、LPO、アフィリエート、バナーなのかもしれないが、これでは一切、種を蒔くことも育てることもなく、目の前に来た客を手招きして、刈り取るだけだ。
現状をリアクティブなマーケティングだとすると、プロアクティブなマーケティングが求められる。それは、モニタリング、エンゲージメント、レスポンス、ダイアログだ。手間とコスト、時間がかかるマーケティングだ。
最後に「ザッポスの奇跡」を購読されることをお薦めします。