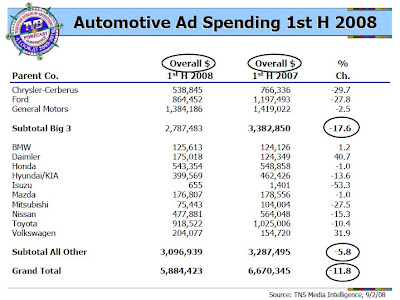以前、「RIM MJ」を書いた。
参考:
RIM MJ (Online Ad 2009/06/27)
その絡みでちょっとFacebookを確認したところ、Michael JacksonのFacebookにあるPageには、すでに780万人以上(7月9日時点)のFanがついている。今朝はもう877万人を超えている。あっという間にObama大統領を追い抜いてFacebookで最もFanを抱えているページになっている。
InsideFacebookによれば、7月8日だけで90万人以上、1週間で454万人以上がFanになっている。チョー強烈な伸びだというほかはない。

MJのWallには、ライブ追悼式の件、追悼式の告知、無料ギフトなど上がっている。

そして、MJのFanになった筆者のFacebookページには、他のFanや友人が書き込んだコンテンツと一緒にMJコンテンツも反映されている。

ということで、Facebookは世界中に友達の輪が広がってゆくネットワークであり、コンテンツの流通チャネルであり、露出増幅マシーンでもある。
また、Facebookをメディアと捉えるとMJの場合、877万人もの読者、聴取者、視聴者がいる自前メディアを持っていることになる。自前メディアなのでコストはかからない。
既成レガシーメディアであれば双方向のコミュニケーションはもちろん存在しないし、ワンウェイのコミュニケーションを行ったところでそれを他人が知る術はない。最初から会話が成立するベースは存在していない。また、メディアから押し付けられるコンテンツを受け入れるか、あるいは拒絶するかの選択肢しかない。
ところがオンラインのソーシャルメディアスペースで最大であるFacebookのページ、Wallであれば、MJからのコンテンツも、Fanからのコンテンツもオープン、透明に供給され、消費され、共有され、再露出されているし、会話が成立する。
こういったコミュニケーションチャネルこそ、企業・ブランドが昔から、広告というメッセージを発信した時から希求していたものだ。いや、最初はマスメディアを使うことで露出を稼ぎ、押し売りするメリットを最大化しようとしていただけなのかもしれない。
しかし、2006年のANA総会でP&GのCEO、A. G. Lafleyが、
「
パワーは消費者が握っている」
「マーケターおよび小売業者は、消費者にしがみついて後れないようについて行っている」
P&Gは長い間、消費者がどのように商品を理解、使用すべきかを教えてきたが、
「DVRや衛星ラジオなどの技術を使った広告を、いつ見たり、いつ消すかを消費者が選択している今日、小売側は消費者とともに学んでいる段階だ」
「
消費者があらゆる意味で我々のブランドを所有し、ブランド創造にも参加している」
「我々は、消費者や好きな製品の回りに築かれるオンラインコミュニティによってコマーシャルが創造されるこのトレンドを認めるべく学習すべきだし、それを歓迎すべきだ」
と述べているように、「トップダウン方式のマーケティングからボトムアップ、グラスルーツ方式のマーケティングへ変えていかなければならない」という理解は広まり、実践するケースが増えこそすれ、少なくなったり、消えてゆくようなことはない。そして、現在、ボトムアップ、グラスルーツ方式のマーケティングの中身が変化してきている。
参考:
Letting Consumer Control Marketing : Priceless (Online Ad 2006/10/17)
話をFacebookに戻すと、ボトムアップ・グラスルーツ方式から、参加、共有、コラボ、拡散、再露出というソーシャルメディアマーケティングへ移行してきた状況で、そのメディア・コミュニケーションシーンのトップに立つFacebookを活用することで、既存メディアの存在意義が薄まってくる。
なにしろコストのかからないメディアなど今まで存在していなかったのだから。レガシーメディアへの広告がなくなることはない(だろう)が、そのシェアは減るしかない。

参考:
Beyond Advertising (Online Ad 2009/04/30)
新聞や雑誌広告、TVCFに金をかけ、仰々しく額装丁されたエビデンスプレートをオフィスに飾るステータスとしてのレガシーメディアが全てを牛耳っていた時代から、一般消費者・ユーザ・顧客が手綱を握るソーシャルメディアへ参加することで初めてコミュニケーションが成立する時代へ変わってきている。
こういった時代にレガシーメディアに広告を出しているだけで、ソーシャルメディアスペースで露出することもできないし、参加することなど全くできはしない。今こそ、マインドセットをシフトする時なのだが...。
 そして、中国では1990年代中ごろにカラーTVの出荷が急増した。8~10年というTV寿命からすると4.5億台のCRT TVが、これからの5~10年の間にFPD TVに切り替えられると予想している。その結果、世界市場で見ると、2011年には米国市場を抜くと予想されている。
そして、中国では1990年代中ごろにカラーTVの出荷が急増した。8~10年というTV寿命からすると4.5億台のCRT TVが、これからの5~10年の間にFPD TVに切り替えられると予想している。その結果、世界市場で見ると、2011年には米国市場を抜くと予想されている。 Source:DisplaySearch / China FPD TV Market on Track to Surpass 50M by 2012
Source:DisplaySearch / China FPD TV Market on Track to Surpass 50M by 2012